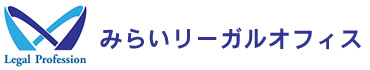人には、「相続しない」という権利がある
最愛の家族が亡くなり、悲しみに暮れる暇もなく襲ってくるのは「法」で縛られた悲しい現実かもしれません。
まさか、このような借金があったとは…
まさか、保証人になっていたとは…
相続人は、法律上プラスの財産だけでなく、マイナスの財産、つまり借金などの負債も相続します。このことは、相続人の意思にかかわらず、法的に当然に生じてしまいます。したがって、亡くなられた親などの「被相続人」が負債を抱えていた場合、相続人は、原則として法定相続分に応じて、それらの負債の返済義務を負うことになります。
しかし、被相続人にめぼしい財産がなく、負債だけ抱えて亡くなられた場合などに、相続人は、自身の意思により相続放棄をして、はじめから相続人とならなかった状態にすることができます(民法939条)。
相続放棄は、時間との闘いと言われています。原則として被相続人が亡くなってから(亡くなったことと、自分が相続人であることを理解したときから)3か月以内に申立てをしないといけないからです。ただし、相続人が、被相続人に負債があることを知らなかった場合は、請求書が届くなどして負債の存在を知った時から3か月以内に申立てをすることになります(最高裁判所昭和59年4月27日判決)。
相続放棄に関する疑問
顔も分からない親の借金も相続するのか?
幼い頃に両親が離婚して母親に育てられ、それ以来、父親とは音信不通の状況にあります。最近、突然、父名義の借金の請求が私あてに届きました。通知をよく読むと、父が亡くなり、その借金を私に払え、というもののようです。これまでに、親子として生活をしたことがなく、顔も分からない父親の借金を、父が亡くなると私が返済しないといけないのでしょうか…
回答
いくら長年会うこともなく、事実上、親子の関係ではなかったとしても、法律上は親子であり、相続人として子は、法定相続分に応じた返済義務があります。例えば、相続人が子供2人の場合は、各2分の1ずつ、あなた1人が相続人の場合、借金の全額を支払う義務があります。
なお、相続人が複数いても、その相続人が相続放棄をした場合は、相続人とはみなしませんから、相続人の数には入れません。
したがって、このまま何もしないと、あなたが父親の借金の全部または一部を引き継いでしまうことになります。また、借金だけでなく、例えば、父親が生活していた住居に残された残置物の撤去や家賃の清算など、様々な負担を相続人として背負うことになります。
このようなケースでは、請求書等が届き、父親に負債があったことを知った時から3か月以内に、父親が亡くなった時の住所地の管轄裁判所に、相続放棄の申立てをすることになります。
まずは、父親が亡くなった事実や住所地を確認するため、戸籍等の調査から始めることになります。
相続放棄と遺産分割協議は違う
父親が数年前に亡くなりました。父は生前、事業を営んでいて、長男である兄が事業を引き継いでいます。他の相続人は、長女の私だけです。
父の法事の際、兄に頼まれて、遺産分割協議書に署名・捺印しました。同協議書の内容は、兄が自宅や事業に関する財産の全て及び事業資金として父が借りた銀行融資の全てを相続する、という内容のものです。私は、借金も兄が相続するのであればいいだろうと思い、協議書の内容に同意、署名し、自宅や事業に関する不動産は全て兄名義に移しました。
しかし、兄が引き継いだ事業の経営が思わしくないようで、最近になって、父が融資を受けた事業資金について、私にも返済義務があるとして金融機関から請求を受けています。遺産分割協議では、兄が負債を引き継ぐということから、財産を全部、兄に移すことに同意したのに、私にも父の借入金を返済する義務があるのでしょうか。
回答
遺産分割協議により、被相続人の借入金を一部の相続人が承継する、という内容の協議が成立し遺産分割協議書が作成されても、借入金の債権者にはそのことを主張できません。ご相談の事例でいえば、仮に、兄が相続した借入金を返済できなくなった場合、あなたは法定相続分に応じた返済義務を負うことになります(東京高等裁判所昭和37年4月13日決定)。
したがって、このようなケースでは、財産を全く取得しない相続人は、遺産分割協議ではなく、相続放棄も検討するべきであったと考えます。
このようなことは、専門家が関与する手続きでも注意が必要であると考えます。例えば、不動産の相続登記をするために、遺産分割協議の中で、安易に「特別受益証明書」等の書面を作成し不動産を相続しない相続人に署名させ、便宜的に不動産だけを一部の相続人に移転させるというような、負債のことをほとんど意識していないと思われる事例が少なからず見受けられます。
このようなケースでは、印鑑を押す前に、負債がどうなるのか、しっかりと専門家などの第三者に確認すべきでしょう。
なお、本件のようなケースでも、債権者である銀行等の金融機関の関与の下、相続した借入金について、兄も含めて「免責的債務引受」という契約を結ぶことにより、あなたについて免責の合意ができれば、その債務については責任を免れられ、兄が返済できなくなっても請求を受けることはなくなります。しかし、あくまでも債権者の承諾等、その関与が必要となりますので、必ず事前によく確認をする必要があります。
上記のケースですと、原則として相続放棄は亡くなってから3か月以内の申立てが必要になりますので、プラスの相続財産を相続しない相続人は、相続放棄も検討すべきであると思われます。
相続放棄の注意点 子供全員が相続放棄をすると…
夫が自宅の土地・建物と負債を抱えて亡くなりました。自宅は、妻の私(A子)名義にするつもりです。成人の子供たち全員が、「自宅はいらないし、負債も背負いたくない」と、相続放棄をすると言っています。夫の財産は、全て私が相続できますでしょうか。
回答
このケースでお子さん全員が相続放棄をしてしまうと、相続人は、妻であるA子さんだけでなく、ご主人の親がいれば親に、親がすでに死亡しているなど相続人でない場合は、ご主人の兄弟姉妹(それらが死亡している場合はその子)にも、一部相続されてしまいます。したがって、お子さん全員が相続放棄をしてしまうと、ご主人の財産を全てA子さんが相続できるわけではなく、ご主人の親や兄弟等も関係してくることになりますので、十分な注意が必要です。
ちなみに、このケースでお子さん方の立場から考えると、お子さん方は、A子さんが亡くなった時点で存在する自宅と負債を相続をするか放棄するかを、再度検討することになります。
借金以外の理由(面倒に巻き込まれたくない)で相続放棄はできるか
親族が亡くなり、私が相続人の一人であるという連絡を受けました。その親族に借金などの負債があるかどうかは不明です。しかし、面倒なことに巻き込まれたくありません。私は、相続放棄をすることは可能でしょうか。また、相続放棄をするには、ほかの相続人の同意を得る必要はありますでしょうか。
回答
上記の連絡を受けてから3か月以内に相続放棄の申立てをすることができます。また、ほかの相続人の同意を得る必要はなく、単独で手続きができます。相続放棄をするには、裁判所に放棄する理由を申述する必要がありますが、その理由として債務超過(借金)だけが必要な要件、というものではありません。
人が死亡すると、その人に借金がなくても、相続人には様々な負担が生じることはやむを得ないことだと思います。例えば、借家やアパート住まいであれば、部屋に残された残置物の処分をする義務や、持ち家が老朽化した家屋であれば、その管理義務や近隣住民へ損害を与えないように配慮する義務など、重い負担が生じます。しかし、特に別居の親族であれば、今後、どのような負担が発生するかは予測が難しいでしょう。相続放棄をして負担を免れたい、と考えるのも自然なことだと思います。
このような場合、みらいリーガルオフィスでは、放棄の理由を、例えば、「被相続人とは長年疎遠であり、同人の権利・義務を承継したくないから」とし、プラス、マイナスの財産の有無を問わず、相続を放棄する意思であることを裁判所に申述する書類を作成します。
ただし、後日、その親族に高額の財産の存在が判明しても、放棄の撤回は認められず、その財産を相続する権利はなくなりますので、十分にご理解のうえ、手続きを進めるようにしてください。
遺産分割協議をした後に、相続放棄はできるか
亡くなった父に借金があることを知らないで、兄との間で遺産分割協議をしました。内容は、唯一の財産である自宅を兄が相続するというもので、私が受け取る遺産はありません。しかし、その後、亡くなった父に借金があったことが判明しました。相続放棄をすることは可能でしょうか?
回答
遺産分割協議をすると、その相続については「単純承認」とみなされ、相続放棄ができないのが原則です。しかし、ケースによっては、相続放棄が認められる場合もあります。裁判例では、多額の相続債務の存在を知らずに遺産分割をしたケースで、遺産分割協議を要素の錯誤により無効とし、法定単純承認の効果も生じないとみる余地があるとして、遺産分割協議の無効、すなわち、相続放棄の有効性を認めたものがあります(大阪高等裁判所平成10年2月9日決定)。
この裁判は、最高裁判所の判断ではありませんので、全ての事例に適用されるというものではありません。しかし、みらいリーガルオフィスでは、相続債務の存在を知らずに遺産分割協議で財産を他の相続人が相続したケースで、借金の存在を知った時から3か月以内に申立てをした相続放棄が受理された事例がありますので、同様のケースでお悩みの方はご相談ください。
なお、上記のケースでも負債の存在が発覚してから3か月以内に申立てをする必要があり、また、財産の一部を処分したりした場合は、法定単純承認(民法921条)として相続放棄ができなくなりますので、ご注意ください。
相続人に未成年者がいる場合
主人が借金だけを残して亡くなりました。相続人は、私と未成年の子2人です。子供たちは、相続放棄をすることができますか?
回答
未成年のお子さんの相続放棄は、あなたが法定代理人として、ご自身の分と一緒に手続きをすることになります。
ご質問のケースで、お子さんだけを相続放棄させる場合は、お子さんについて特別代理人を選任する必要がありますが、債務超過の場合にお子さんだけ相続放棄させることはないでしょうから、あなたが二人のお子さんの法定代理人として、ご自身の分と一緒に相続放棄の手続きをすることになります。
なお、あなたが、お子さんより先に相続放棄をしている場合やご主人の死亡前に正式に離婚していた場合は、お子さんについてのみ相続放棄をすることになります。
なお、配偶者である妻及び子の全員が相続放棄をすると、ご主人に親がいれば親が相続人となり、その親が相続放棄をした場合または両親とも亡くなっている場合は、ご主人の兄弟姉妹が相続人となり、借金の請求がそちらに行く可能性があります。ご主人の親族と交流があるなど、無視できない関係性であれば、相続放棄をしたことを知らせたほうがいいかもしれません。みらいリーガルオフィスでは、その場合の通知も代行しています(追加の費用はありません)。
ちなみに、第2順位以後(親や兄弟姉妹等)の相続人は、先順位の相続人の相続放棄が裁判所に受理された時から、3か月以内に相続放棄の申立てをすることになります。
相続放棄をすると、生命保険金は受け取れなくなるか
主人が、めぼしい財産もなく、借金だけを残して亡くなりました。しかし、主人は私を受取人とする生命保険に加入していました。相続放棄をした場合、生命保険金は受け取れなくなってしまうのでしょうか。あるいは、受け取った保険金から、借金の返済をする必要があるのでしょうか?
回答
奥様を受取人とした死亡保険金は、奥様固有の財産として問題なく受け取ることができ、そこから借金の返済をする必要はありません。ただし、ご主人がご自身を受取人としていた場合は、相続放棄をすると保険金は受け取れなくなりますので、借金額と保険金の金額により、相続放棄の可否を検討することになるでしょう。
相続放棄手続きの流れ
1 ご相談(無料)
・事務所に起こしいただくのが難しい方は、電話・メール・郵送によるお手続きも可能です。
↓
2 お見積り(無料)
・基本的にホームページ記載の金額と同額です(追加の請求はありません)。
↓
3 契約(手続きのお申込み)
↓
4 手続きの着手→戸籍等収集 裁判所に必要書類を提出
費用のご入金(お振込み等)
↓
5 照会書の送付(作成、助言)
↓
6 裁判所から受理証明書を受領
↓
7 債権者・親族等への通知(必要な場合)
↓
8 終了(裁判所の受理証明書をご郵送)
※手続きのお申込みから終了まで、通常、1か月~2か月程度です。
相続放棄の費用
続放棄手続(フルサポート)
裁判所提出書類作成、裁判所への提出代行、戸籍謄本等の取得、印紙代、裁判所からの照会の対応、受理証明書取得、債権者・他の親族への通知等(必要な場合)、一切を含みます
相続放棄される方の人数・費用(税込)
一人・55,000円
二人目~・35,000円(1人につき)
相続開始後3か月経過後・一人につき10,000円を加算
・通信費としてお一人5,000円かかります。
・上記報酬額は、最低額ではありません。完全定額制です。
例えば、お一人の場合は60,000円(税込)、お二人の場合は100,000円(税込)、お三方の場合は140,000円(税込)が総額となります。
・すでに取得されている戸籍等がある場合、費用からその分を減額します。
・相談は無料です