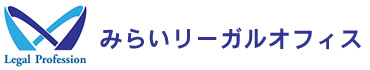自己破産とは
自己破産は、原則的には、裁判所が債務者(破産する人)が持っている財産を売却等してお金に換え、各債権者に平等に分配する手続きです。しかし、テレビや冷蔵庫などの家財道具は財産のうちに入りません。したがって、現在、破産の申立てをする一般人の方のほとんどは、財産が存在しませんので、財産を清算する手続きは行われず(破産管財人を選任しない)、もっぱら、破産申立ての目的は「免責」を受けて、法的に借金を返済しなくてもいい状態にすることです。
借金の総額が、年収を超えているような方、返しては借りるという繰り返しの状況に陥っている方は、自己破産も解決策の一つとして検討したほうがいいでしょう。
免責について
自己破産の最大の特徴は、「免責」を受けて、法的に借金全額の免除を受けられることです。破産法では、免責が認められない「免責不許可事由」が定められており、ギャンブルや浪費等によって借金の多くを抱えた人などには免責を与えないのが原則です。したがって、免責不許可事由に該当する方は、個人再生手続きによって、解決を図ることも検討したほうがいいでしょう。
しかし、免責不許可事由に該当する場合でも、よほど悪質なケースでなければ、免責が認められる場合も少なくありませんので、経験豊富な司法書士などに相談し、裁判所に反省の態度を書面にして示すなどして免責を得られるような措置を講じてもらいましょう。専門家に依頼しないで破産の申立てをされた方が、書類の書き方がよくなかったために、「免責不許可」と裁判所から判断されたようなケースも見受けられますので、書類の作成には十分な注意が必要です。
財産(生命保険、自動車、退職金等)がある場合
以下の取り扱いは、地域(管轄裁判所)によって異なる場合があります。
生命保険
生命保険や学資保険等、資産性のある保険等に加入している場合は、解約したときに戻る金額(解約返戻金)がわかる資料を裁判所に提出する必要があり、その金額が財産とみなされます。解約返戻金が20万円を超えるような場合には、裁判所から保険を解約し、各債権者に配当するように指示される可能性があるので、手続きの申し立て前に解約して税金の滞納分や破産申立費用に充てることも検討すべきでしょう。しかし、解約した返戻金の使途は、法的に限定されており、不当な返済(偏波弁済)とされないよう、専門家の関与の下で行うべきです。
また、解約返戻金が他の財産を含め、20万円を超えるようなケースでは、裁判所が破産管財人を選任する場合があります。破産管財人が選任されると、費用として最低でもプラス20万円程度必要になり、また、郵便物の全てが、一度破産管財人に配達されたりするので、破産管財人が選任されそうなケースでは、個人再生手続きとの比較も検討すべきでしょう。
自動車について
ローンのない比較的年式の新しい自動車(登録後5年以内程度)は、自動車販売業者などに査定をしてもらい、その金額が財産とみなされます。
銀行等の金融機関のマイカーローン、フリーローン等を利用して車を購入し、ご自身名義で登録した場合などもこれに含まれます。したがって、その車の財産的価値が一定金額(原則20万円)以上になる場合は、原則として、裁判所によって売却処分されてしまいます。したがって、このようなケースでは、個人再生手続きも検討することになります。
自動車ローンが残っている場合には、車の所有権はローン会社にあるの一般的ですので、原則として、ローン会社に車を引き上げられて売却処分され、不足分を借金額として破産の手続きに加えます。
このローンに保証人がいる場合は、車両引き上げ後の残金について、ローン会社が保証人に対して一括返済を求めることになります。場合によっては、車を保証人等にローンの残金分で売却し、車の名義を保証人等に変更したり、債権者の同意を得て保証人から返済を継続するということで、このまま車を使用することができる場合もありますが、保証人とクレジット会社との合意が必要になります。いずれにしても、このような手続きを行うには、後日問題が起こらぬよう、専門家の助言・関与が不可欠です。
退職金請求権も財産
破産をしても、一部の職業を除いて仕事を辞めなければならないようなことはありません。しかし、退職をしないとしても、破産の申立てをした時点での退職した場合の退職金額の一部は財産とみなされます。その割合は裁判所によって異なりますが、茨城県内の裁判所の場合、原則として自己都合退職の退職金の8分の1を財産とみなします。仮に、この退職金が800万円だとすると、その8分の1の100万円が財産とみなされます。このケースでは、破産の申立て後、100万円を用意(積立等)して、破産管財人によって債権者に対する配当が行われるまが原則です。
したがって、退職金額が高額になる場合には、破産ではなく、個人再生手続きも検討する必要があると思われます。
破産したらどのような不利益があるのか
戸籍に記載される、選挙権がなくなる、今後旅行に行けない、パスポートが取れない、テレビや冷蔵庫を持っていかれる、家族全員がその財産の4分の1を失う、通帳を作れない、離婚をしたほうがいいと聞いた、など、相談に来る方は色々な情報を持っているようですが、破産をしても全く上記のようなことにはなりません。ただし、生命保険の外交員など、他人の財産を扱うことがあるような職業は、一定期間、仕事が制限されますが、免責が確定(復権)すれば制限はなくなります。
また、破産をすると「官報」という国が発行する機関紙に、住所、氏名が掲載されますが、これは、もっぱら手続きから除外された債権者の保護が目的で、破産した人に制裁を加えるのが目的ではありません。一般の人が官報を見るようなことはありませんから、あなたが破産をしたことは、あなたが誰かに言わなければ、他人に知られることはまずないでしょう。
なお、官報の情報を悪用し、「ブラックリストを○○万円で消します」などの詐欺行為等が横行していますので、だまされないように十分な注意が必要です。なお、過去に破産して免責を受けた人は、その後7年間は再度、免責を受けることができないとするのが法律上の規定ですが、今回の借金の原因等により、裁判所の裁量で免責が認められることもあります。なお、破産免責後7年以内でも、小規模個人再生の申立てをすることは可能です。
自己破産の事例紹介
破産手続きの費用
通常の場合
費用総額 330,000円(税込)
・免責(借金の免除)までフルサポート《手続き完了まで責任をもってサポート》します)・費用は、分割による支払いも可能です(毎月33,000円くらい~)。お気軽にご相談ください。
・実費分(印紙代、予納郵券、通信費)として30,000円程度申し受けます。
・不動産を所有されている場合は、50,000円(税込)程度が加算されます。
・個人事業者の方は、費用が追加される場合があります(50,000円(税込)程度)。
・財産がある等により、破産管財人が選任された場合は、費用の加算があります。
・個人の債権者がいる場合は、費用が追加される場合があります。
生活困窮者等
・母子家庭や少額の年金受給者など、住民税非課税世帯に該当する方などは、少額の費用で手続きが利用できる場合があります(国の法律扶助制度を利用)。
お気軽にご相談ください。